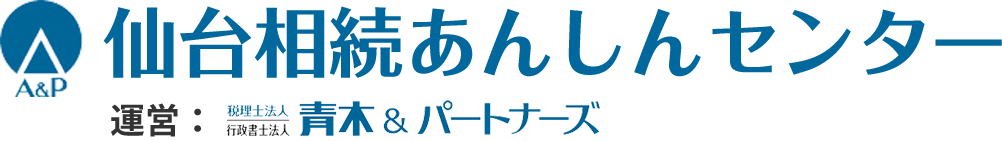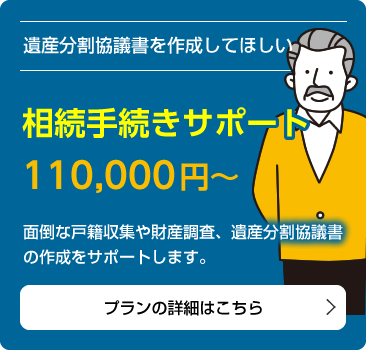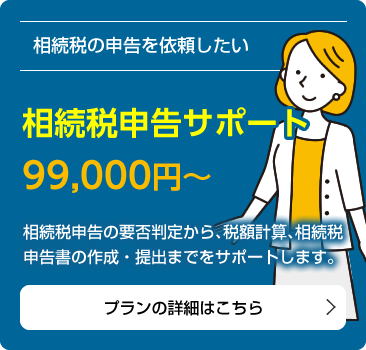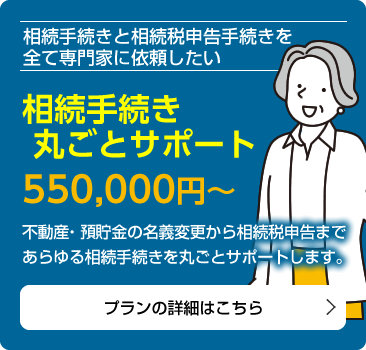相続における養子縁組が与える影響について解説します!
ホーム > 相続豆知識 > [相続人・相続調査] 相続における養子縁組が与える影響について解説します!
相続税の軽減を目的とした養子縁組は、一見すると有効な手段のように思われます。ただし、実際には多くのリスクを伴うため、慎重な判断が必要です。
養子縁組により相続人の数を増やすことで税負担を軽減できるというメリットがあります。 ただし、これが法律的に認められるわけではなく、税務署による否認リスクや、家族間のトラブルを引き起こす可能性があります。
また、養子縁組は税金対策ではなく、法律上・社会的に大きな意味を持つ制度です。この点を軽視すると、後々思わぬ負担が生じることになります。
この記事では、養子縁組の基本的な仕組みから、相続対策としての有効性、そして養子縁組による様々な影響について解説します。
1. 相続における養子縁組とは?基本を理解しましょう
養子縁組とは?
養子縁組とは、血縁関係のない人を法的に「子」とする制度です。
養子になった人は 実子と同じように法定相続人となり、相続権を持つことになります。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、相続対策で活用されるのは普通養子縁組 です。
それぞれの違いは以下の通りです。
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
|---|---|---|
| 縁組の手続 | 養子が未成年でなければ当事者の届出のみ | 家庭裁判所の審判が必要 |
| 養親の要件 | 成人であれば可 | 養親の25歳以上の夫婦のみ可(一方が25歳未満の場合は、その者が20歳以上) |
| 養子の要件 | 養親より年下 | 原則15歳未満 |
| 実親との関係 | 実親との親子関係は存続 | 実親との親子関係は消滅 |
| 相続権 | 養親・実親の両方の相続権を持つ | 養親のみの相続権を持つ |
| 戸籍の記載 | 養子と明記 | 養子ではなく、長男・長女等と記載 |
2. 養子縁組をすると相続税が節税となる理由
相続人である養子が増えると相続税の基礎控除額が増える
相続税の基礎控除額は、
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) で計算されます。
養子縁組をすると 法定相続人の数が増えるため、基礎控除額が増え、結果的に相続税を減らせるという仕組みです。
相続人である養子が増えると「生命保険金の非課税枠」も増える
生命保険の死亡保険金は、法定相続人1人あたり500万円まで非課税という規定があります。
つまり、養子を1人増やすことで、500万円の非課税枠が増加します。
例えば、
相続人が2人の場合(配偶者・実子1人) → 非課税枠 1,000万円(500万円 × 2)
養子を1人増やした場合 → 非課税枠 1,500万円(500万円 × 3)
このように、 養子縁組をすることで相続税の節税効果が生まれます。
3. 養子縁組のデメリットとは?注意点をチェック
養子縁組は相続税対策として有効な手段ですが、いくつかのデメリットやリスクも存在します。養子縁組を行う前に、以下の点を十分に理解し、慎重に判断しましょう。
① 他の相続人とのトラブルの可能性
養子を迎えることで、他の相続人(特に実子)が「遺産が減る」と不満を抱くことがある ため、トラブルが発生しやすくなります。
[トラブルの具体例]
・実子が「養子に遺産を奪われた」と主張
・養子自身が相続争いに巻き込まれる
・遺産分割協議がスムーズに進まない
[解決策]
・養子縁組をする前に、相続人間で十分に話し合う
・遺言書を作成し、財産の分け方を明確にする
・専門家(弁護士・税理士)に相談し、公平な相続計画を立てる
② 養子縁組の人数制限がある
養子を増やすことで相続税の基礎控除額を増やせるとはいえ、税務上の養子の数には制限があるため、注意が必要です。
| 実子の有無 | 相続税法上の養子のカウント |
|---|---|
| 実子がいる場合 | 養子1人まで |
| 実子がいない場合 | 養子2人まで |
この制限を超えて養子縁組を行った場合、相続税の計算上、法定相続人として認められず、節税効果を得ることができない ため、事前に確認が必要です。
③ 一度養子縁組をすると、簡単には解消できない
養子縁組は 戸籍上の手続きが必要 であり、一度養子にすると、簡単に関係を解消できません。
万が一、相続対策として養子縁組を行ったものの後からトラブルが発生すると、縁組の解消が難しくなる可能性があります。
[養子縁組を解消する方法(離縁)]
養子と養親の双方が合意すれば、離縁届を提出できる
養子や他の家族が「縁組は不適切」と主張すると、裁判が必要になることも
④ 養子にも扶養義務が発生する
養子縁組をすると、単に相続人が増えるだけでなく、養親と養子の間に「扶養義務」も生じます。
そのため、将来的に養子の生活を支えなければならない可能性があることを理解しておく必要があります。
[具体例]
・養親が高齢になった場合、養子が介護や扶養の義務を負う
・養子が金銭的に困窮した場合、養親が支援を求められる可能性がある
[事前に確認すべきポイント]
養子と養親の将来の関係を考慮する
扶養義務が発生することを理解した上で養子縁組を行う
⑤ 実子と養子の相続分が同じになる
養子縁組をすると、養子は実子と同じ法定相続分を持つことになります。
そのため、「実子により多く財産を残したい」と考えている場合は、遺言書の作成などの対策が必要になります。しかし、これは相続人間のトラブルに繋がる可能性があります。
[具体例]
・実子が2人、養子が1人いる場合 → 3人で同じ割合の相続権を持つ
・実子に多く財産を渡したい場合は、遺言書や遺贈の手続きを検討する必要がある
[解決策]
遺言書を作成し、具体的な遺産分割の方針を示しておく
生前贈与などを活用して、財産の配分を調整する
4. 養子縁組のデメリットまとめ:相続人間のトラブルの原因になることも
(1)相続税の申告をしましょう!
相続税の節税対策として養子縁組を利用する方法は、一見魅力的に思えますが、実際には相続人同士のトラブルの原因となるケースが多く、慎重な判断が求められます。
養子縁組によるデメリットは以下の通りです。
実子や他の相続人との関係が悪化する
「財産目当ての養子縁組」と疑われる可能性がある
相続人間の公平性を損ない、遺産分割協議が難航する
養子縁組の解消(離縁)が簡単にできず、関係がこじれると大きな問題になる
特に、実子がいる家庭で養子縁組を行うと、実子から「養子に遺産を奪われた」と反発されるケースが多い ため、親族間の争いを引き起こすリスクが高まります。
また、税務上の制限があり、養子縁組をしたからといって必ず相続税の負担が大きく減るわけではありません。
相続対策としての養子縁組は避けるのが無難!
相続税を減らすためだけに養子縁組を利用するのは、かえって家族の関係を悪化させ、遺産分割のトラブルを招く可能性が高いため、おすすめできません。
本当に必要な場合を除き、「相続税対策としての養子縁組」はできるだけ避け、別の方法で相続税対策を考えるべきです。
相続税対策は、養子縁組以外にも様々な方法があります。専門家に相談し、家族関係を損なわない最適な対策を検討しましょう!
5. まとめ:養子縁組は相続対策になりますが慎重に!
法定相続人を増やすことで相続税の基礎控除額や生命保険の非課税枠を拡大できるため、相続税の負担を軽減できます。
しかし、他の相続人とのトラブルや、税務上の制限もあるため、実行する際は慎重な検討が必要です。本当に必要な場合を除き、養子縁組での相続税対策は避けましょう。相続対策に興味がある方は、専門家に相談し、最適な方法を見つけることが重要です。
2025年4月時点での情報です。今後の税制改正や実務運用の変更がある場合には、専門家にご確認ください。
相続に関する無料相談実施中

相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>
お気軽にご相談ください
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台MTビルSOUTH4階
TEL:0120-311-315
FAX:022-295-1372
[受付時間]
平日9:00~18:00(受付:9:00~17:30迄)
土曜9:00~17:00(要予約)