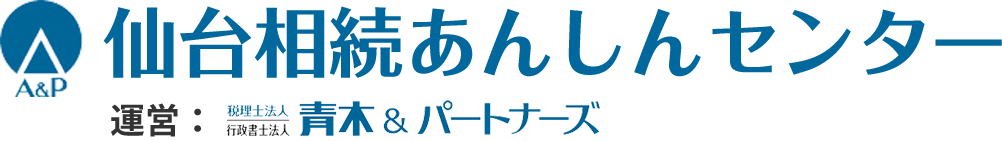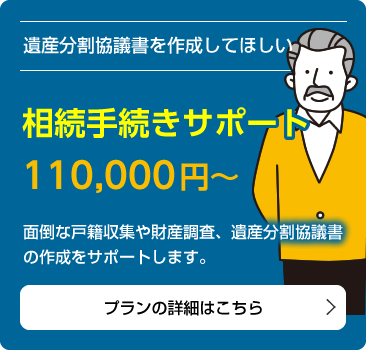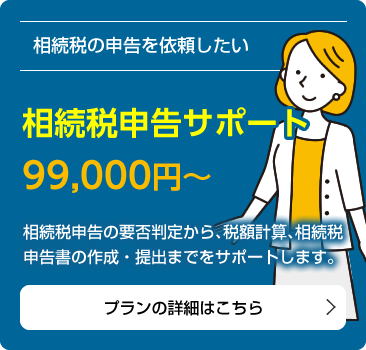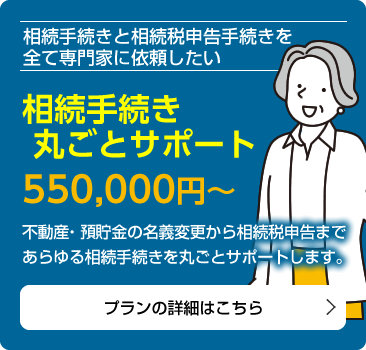相続税の時効は5年/7年?
起算日と無申告がバレる理由・ペナルティを徹底解説
ホーム > 相続豆知識 > [相続税申告] 相続税の時効は5年/7年?起算日と無申告がバレる理由・ペナルティを徹底解説
相続税には時効(除斥期間)という制度があるのはご存じですか?
これは、一定の期間が経過すると税務署が相続税を賦課・徴収できなくなる仕組みです。しかし、「時効を待てば納税しなくて済む」という考えは非常に危険です。税務署の強力な調査体制のもと、無申告や申告漏れはほぼ確実に発覚し、重いペナルティが課されます。
この記事では、相続税の時効の仕組み、時効の起算日、時効が成立する条件、税務署の対応、そして正しい相続対策について詳しく解説します。
1. 相続税の時効(除斥期間)の基本ルール(起算日・期間)
相続税の時効(税法上は除斥期間と呼びます)とは、一定期間が経過すると相続税の納税義務が消滅する制度です。税務署の徴税権を無期限に認めると、納税者にいつまでも負担がかかるため、この期間が設けられています。
相続税は法人税などと同様、申告納税制度を取っています。これは、納めるべき税額が納税者の申告によって確定する仕組みです。しかし、定められた申告期限までに申告がない場合や申告された税額が過少な場合などには、税務署が調査を行い、更正または決定の処分を行うことで追徴税額が確定します。
税務署がこの「更正または決定の処分」を行える期間が除斥期間であり、この期間が過ぎると、追徴の権利が成立しません。(以下、除斥期間を平たく「時効」と表現します。)
相続税の時効期間は、相続税の申告期限の翌日から原則5年です。ただし、意図的な財産の隠蔽など、悪意のある悪質なケースでは7年に延長されます。
時効の期間には、民法上の時効のように更新や中断はありません。そのため、追徴が必要な納税者に対しては、この期間内に税務署が調査を行って追徴税額の通知書を渡さなければなりません。裏を返すと、除斥期間が満了するまでの5年あるいは7年間は、いつ税務調査が入るか分からないということになります。
2. 相続税の時効は原則5年。起算日の考え方と成立条件
相続税の時効は、原則として5年です。これは国税通則法第70条によって定められている一般的なルールです。
重要なのは、この5年という期間は相続発生時点からカウントされるわけではないことです。相続税には申告「期限」があり、この期限の翌日から時効の起算が始まります。
相続税の時効の起算日
- 相続発生日: 被相続人が亡くなった日(この日を入れずに数えます)
- 申告期限: 相続発生を知った日の翌日から10カ月以内
- 時効開始日(起算日): 申告期限の翌日から5年間
具体的な時効成立日の計算例
例えば、2025年1月10日に相続が発生した場合の時効成立日は次のようになります。
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 相続発生(被相続人の死亡日) | 2025年1月10日 |
| 申告期限(10カ月後) | 2025年11月10日 |
| 時効開始日(起算日) | 2025年11月11日 |
| 時効成立日(5年後) | 2030年11月10日 |
このケースでは、2030年11月10日までに税務署が税金を決定・更正しなければ、時効が成立し、納税義務がなくなります。
3. 悪質なケースで時効が7年に延長される「悪意」の判断基準
納税者が財産を隠したり、意図的に虚偽の申告を行ったりした場合は、時効が7年に延長されます。これは、「事実の仮装又は隠ぺい」があったと税務署が判断した場合に適用され、納税者に対してはより厳しいペナルティが科されることになります。
時効が7年に延長される具体的なケースと「悪意」の判断
時効が7年に延長されるのは、納税者が「故意に税を免れようとする悪意」をもって、財産を仮装・隠蔽したと認められる場合です。単なる知識不足による申告漏れや計算ミスは原則5年ですが、以下のような行為は悪質と見なされます。
| ケース | 具体例(悪意と判断される行為) |
|---|---|
| 財産を意図的に隠した | 銀行などの金融機関に知らせずに、相続財産を親族名義に変更する、または海外に送金する。自宅にタンス預金として現金を保管し、その存在を隠す。 |
| 虚偽の申告を行った | 相続財産を過少申告する。存在しない借金や債務を捏造し、財産を偽る。 |
| 一部の財産のみ申告した | 高額な不動産や預貯金など、税務署にバレる確率が低いと考えて一部の財産のみを申告し、残りを隠ぺいする。 |
特にタンス預金や名義預金は税務調査で発覚しやすく、意図的に隠ぺいと見なされれば、時効は7年に延長される上に、重加算税(最大40%)という最も重い罰則が課されます。
4. 「無申告でも時効で逃げ切れる」が不可能な理由
相続税の時効は原則5年、悪質な場合は7年ですが、この期間が過ぎるまで待っていれば相続税の支払い義務がなくなることは、現実的にはほぼ不可能です。多くの方が「税務署は人手不足だからバレないだろう」「預金を隠せば税務調査は来ないだろう」と考えがちですが、それは大きな間違いです。

税務署はKSK(国税総合管理)システムで相続財産を把握している!
税務署は、無申告者や申告漏れの疑いがある人を効率的に特定するために、KSK(国税総合管理)システムという強力なデータベースを活用しています。
このシステムには、全国の税務署が収集したあらゆる財産情報が直ちに共有・管理されています。
- 銀行口座の取引履歴:生前贈与などの履歴も含め、過去数十年にわたる記録。
- 不動産の所有状況:法務局の情報と連携し、全国の土地・建物の所有権の移転を把握。
- 生命保険の契約情報:保険金の支払いは税務署に通知されます。
- 証券・株式の保有状況:金融機関の情報を網羅。
- 過去の納税履歴:所得税、贈与税などの申告履歴。
相続が発生すると、税務署はすぐにこれらの情報と申告書の内容を照合します。申告書が提出されなかった場合、システムが自動でフラグを立て、税務調査の対象となります。つまり、「申告しなければバレない」という考え方は通用せず、無申告者は非常に高い確率で税務調査の対象となり、時効を待つまでもなく発覚する理由はここにあります。
5. 相続税の時効を狙うことの危険性!ペナルティ(罰則)を解説
相続税は、被相続人が亡くなった事実を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付しなければなりません。この期限内に正しい手続きを踏まない場合は、さまざまなペナルティが課されます。この章では、相続税の申告漏れや無申告によって課される「延滞税」「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」について解説します。
延滞税とは?
相続税の納付期限を過ぎても税金を支払わない場合に課される、利息に相当する税金です。
納付期限の翌日から日割りで発生し、放置するほど金額が増加するため、速やかな納付が必要です。
延滞税の計算方法
未納となっている税額と延滞期間の長さに応じた税率をかけて計算します。
| 期間 | 税率(年率)※令和4年以降の例 |
|---|---|
| 納付期限から2カ月以内 | 2.4% |
| 納付期限から2カ月超 | 8.7% |
無申告加算税とは?
相続税の申告期限を過ぎても申告しなかった場合に課される税金です。
税務署から指摘がある前に自主的に期限後申告すれば軽減措置がありますが、調査が入ってから申告をした場合は税率が上がります。
無申告加算税の計算方法(加算税額=追徴税額×下記税率)
| 相続税額 | 自主的に期限後申告 | 税務調査の事前通知後に期限後申告 | 税務調査後に期限後申告 |
|---|---|---|---|
| 50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |
| 50万円超 300万円以下の部分 |
5% | 15% | 20% |
| 300万円超の部分 | 5% | 25% | 30% |
過少申告加算税とは?
相続税を申告しても申告内容に誤りがあり、本来より少ない金額を申告していた場合(申告漏れ)に課される税金です。
税務署の指摘後に修正申告をすると、追加で加算税が発生します。自主的に修正申告を行った場合は、加算税は免除されます。
過少申告加算税の計算方法(加算税額=追徴税額×下記税率)
| 追加で納める相続税額 | 自主的に修正申告 | 税務調査の事前通知後に修正申告 | 税務調査後に修正申告 |
|---|---|---|---|
| 当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分 | なし | 5% | 10% |
| 当初の納税額と50万円のいずれか多い方を超える部分 | なし | 10% | 15% |
重加算税とは?
意図的に財産を隠ぺい、虚偽の申告を行った場合に課される最も厳しいペナルティです。
財産を隠ぺいし、悪質な行為が顕著な場合、相続税本税に加えて追徴税額の35~40%の重加算税が課されます。時効が7年に延長される悪意のあるケースでは、この重加算税が適用されることが多くなります。
重加算税の税率(加算税額=追徴税額×下記税率)
| 状況 | 税率 |
|---|---|
| 財産を隠ぺいして過少申告 | 35% |
| 財産を隠ぺいして無申告 | 40% |
6. 知っておきたい!時効が関係するその他の相続税の「お金」の悩み
相続税の時効について考えるとき、無申告や申告漏れだけでなく、払いすぎた税金(還付)や納付が遅れた場合(滞納)についても知っておくことが大切です。これらも時効(除斥期間)の影響を受けるためです。
相続税の「払いすぎ(還付)」にも時効がある
もし、申告した相続税を払いすぎていた場合(過払い)、税務署に税金の還付(返還)を請求することができますが、これにも期限があります。この期限は、法定申告期限から5年と定められています。払いすぎが発覚したら、速やかに還付の手続き(更正の請求など)を行う必要があります。特に、土地の評価を誤って高く申告していたケースなどで還付が可能となる場合があります。
納付漏れや滞納の時効は「納税の義務」の時効と異なる
無申告や申告漏れによる課税決定の時効(賦課権の除斥期間)は、上述の通り5年または7年です。
これに対し、税務署から納付すべき税額が決定された後に、その税金を納めないまま放置した場合の「納税の義務」の時効(徴収権の消滅時効)は、国税徴収法により原則5年と定められています。
しかし、この徴収権の時効は、税務署からの督促状の送付などにより中断し、新たに起算されます。そのため、滞納による時効の成立は非常に難しく、現実的には不可能だと考えるべきです。
7. まとめ:相続税のペナルティは重い!最初から正しく申告を
相続税の時効は原則5年、悪質な場合は7年です。しかし、税務署のKSKシステムをはじめとする強力な調査体制があるため、「時効を待てば逃れることができる」という考え方は通用しません。
無申告や申告漏れがあった場合、本来の相続税に加えて、重加算税(35~40%)や延滞税(最大8.7%)といった厳しいペナルティが課され、結果的に納税額が大幅に増加する可能性が高くなります。
つまり、最初から正確に申告し、不要なリスクを回避することが、最も安全で賢い選択です。
相続税の申告に不安がある場合は、早めに税理士に相談し、適切な申告を行いましょう!当法人では、相続税申告の実績が豊富な専門家がしっかりと対応させていただきます。具体的なご相談は「無料相談窓口」を設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続に関する無料相談実施中

相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>
お気軽にご相談ください
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台MTビルSOUTH4階
TEL:0120-311-315
FAX:022-295-1372
[受付時間]
平日9:00~18:00(受付:9:00~17:30迄)
土曜9:00~17:00(要予約)