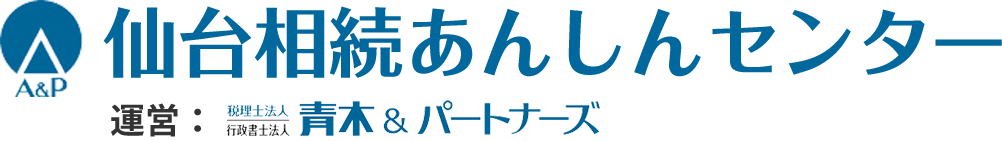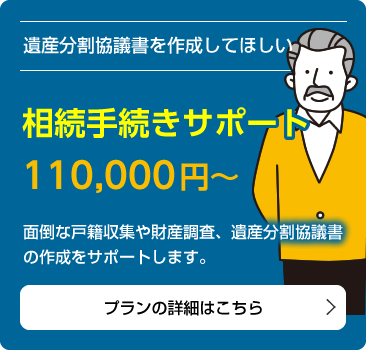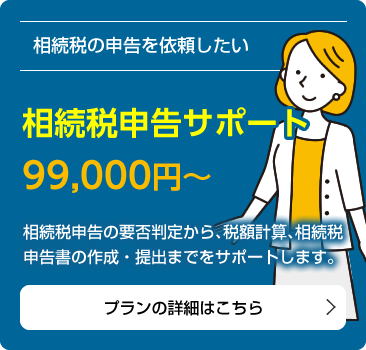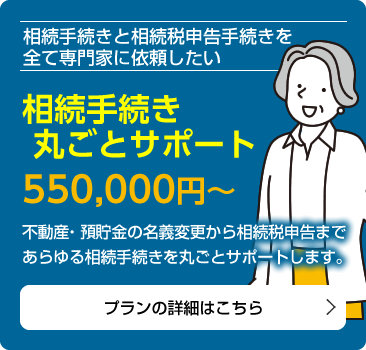相続税申告に残高証明書は必要?必要なケースや発行方法について解説
ホーム > 相続豆知識 > [相続税申告] 相続税申告に残高証明書は必要?必要なケースや発行方法について解説
1. はじめに
相続が発生したとき、「残高証明書」という書類を求められて初めて耳にする方も多いのではないでしょうか。
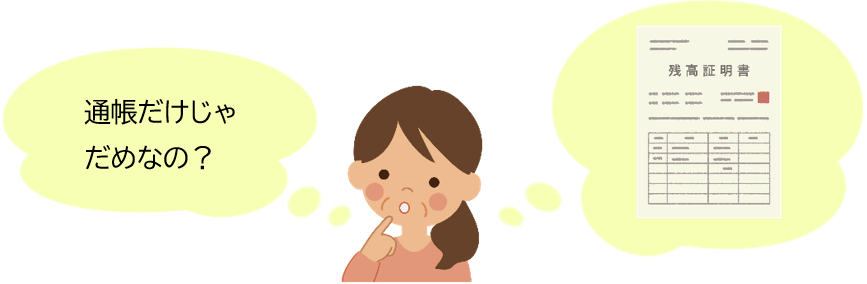
通帳が手元にあるから大丈夫と思っていても、相続税の申告や遺産分割の際には「残高証明書」が重要な役割を果たします。
そもそも残高証明書とはどのような書類なのか、なぜ相続税の申告で必要になるのか、そして実際にどのように発行を依頼すればよいのか───。
この記事では、これらのポイントをわかりやすく解説します。
2. 残高証明書とは?
残高証明書とは、金融機関が発行する「特定日時点の残高」を証明する書類のことです。
預金口座の通帳には日々の取引が記録されていますが、「相続開始時点(=被相続人の死亡日)」の正確な残高を示すものではありません。
そのため、相続税申告の際には、通帳ではなく金融機関が発行する残高証明書をもとに金額を確定する必要があります。
| 書類名 | 残高証明書(預金残高証明書・投資信託残高証明書など) |
|---|---|
| 発行元 | 銀行・信用金庫・証券会社 |
| 記載内容 | 対象口座番号、口座名義人、残高基準日、金額 |
| 基準日 | 相続発生日(被相続人の死亡日)を指定することが一般的 |
| 使用目的 | 相続税申告・遺産分割協議・金融機関手続きなど |
3. 相続税申告で残高証明書が必要になる理由
①相続発生日時点の正確な金額を証明するため
通帳残高は変動するため、死亡日時点での金額が確実にわかる証明書が必要です。
②税務署に提出する正式な証拠となる
金融機関が発行する公的文書としての信頼性があります。
③相続人同士のトラブル防止
「亡くなった後に引き出された金額」などの使途不明金を明確にできます。
相続税の計算は、被相続人が亡くなった時点で所有していた全財産の評価額に基づいて行われます。
そのため、通帳の残高ではなく、「死亡日時点で確定している金額」を証明できる書類が必要になるのです。
例えば、ほとんどの銀行では、一定期間通帳に記帳していなかった場合、入金・出金ごとに合計件数・合計金額をまとめて記帳(一括記帳)しています。その場合、死亡日時点での正確な残高が分からないことがあります。
そのような場合でも残高証明書があれば、「相続開始日現在の正確な残高」がわかるため、後日のトラブル防止にもつながります。
4. 残高証明書が必要となる主なケース
相続税申告以外でも、残高証明書が求められる場面はいくつかあります。
| ケース | 残高証明書の必要性 |
|---|---|
| 相続税の申告を行う場合 | 必須。すべての取引金融機関から取得が望ましい。 |
| 預金の解約・名義変更を行う場合 | 銀行によっては提出を求められる。 |
| 遺産分割協議を行う場合 | 客観的な財産把握のために重要。 |
| 税務調査への対応 | 後日の確認資料として提出が求められることも。 |
「残高証明書が不要」といわれるのは、財産総額が基礎控除以下などで申告義務がない場合に限られます。
実務上は、相続人間の話し合いを円滑に進めるためにも、全口座分を取得しておくのがおすすめです。
5. 残高証明書の発行方法
金融機関によって手続き方法は異なりますが、一般的には以下の3つの方法があります。
① 金融機関の窓口で申請
最も確実で、担当者の説明を受けながらその場で手続きを進められる方法です。
銀行の「相続手続き窓口」で申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や届出印、戸籍関係書類などを提出します。
書類の不備があった場合でも、その場で確認・修正できるため、相続人が複数いる場合や内容に不安がある方におすすめです。
② 郵送による申請
遠方に住んでいる場合や、複数の銀行に手続きが必要な場合に便利です。
銀行のホームページから申請書をダウンロードするか、コールセンターに連絡して書類を取り寄せます。
ただし、書類の記入ミスや不足があると再提出を求められることもあるため、提出前の確認が重要です。
▼ 補足
一部の銀行では、インターネットバンキング上で残高証明書の発行申請ができる場合もあります。ただし、相続発生後の申請ではオンライン手続きが利用できないことが多く、窓口または郵送での対応が原則です。利用している金融機関がオンライン申請に対応しているかどうか、事前に公式サイトなどで確認しましょう。
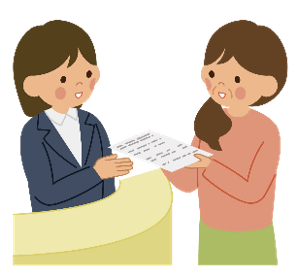
| 書類の区分 | 内容・具体例 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 被相続人の死亡を証明する書類 | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 被相続人が確かに亡くなっていることを証明する書類。多くの銀行では、出生から死亡までの一連の戸籍を求められます。 |
| 相続人であることを証明する書類 | 相続人全員分の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図 | 誰が相続人であるかを明確にするために必要です。法定相続情報一覧図を提出すれば、複数の戸籍をまとめて代替できます。 |
| 相続人代表者の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど | 相続人のうち、銀行とやり取りを行う代表者(代表相続人)が提示します。郵送の場合はコピーの提出が一般的です。 |
| 印鑑 | 申請書への押印に使用。金融機関によっては実印を求められる場合がある。 | 相続人全員の印鑑が必要となるケースもあります。 |
6. 申請時に必要な書類一覧
※金融機関によって申請書類の形式、必要な書類が異なります。
書類を揃える前に、取引のある銀行窓口または公式サイトで最新の必要書類を確認しておくと安心です。
7. 申請時の注意点
残高証明書を依頼するときは、以下のポイントに注意してください。
①発行基準日は必ず「死亡日」にすること
「申請日現在」と記入してしまうと、相続開始日と金額がずれてしまいます。
②支店ごとに申請が必要
同じ銀行でも、複数の支店に口座がある場合、それぞれで申請が必要です。
③発行手数料を確認しておく
1通あたり手数料がかかります。
④証券口座や保険契約も対象
投資信託・株式・保険会社の契約も「残高証明書」に相当する書類を発行してもらえます。
8. 残高証明書をスムーズに取得するためのコツ
相続人が複数いると、書類の取り寄せだけで数週間かかることもあります。
効率よく進めるためのポイントを押さえておきましょう。
①相続人代表を1名に決める
銀行とのやり取りを一元化すると手続きがスムーズです。
②事前に金融機関へ電話で必要書類を確認する
金融機関や支店ごとに異なることがあるため、確認を怠らないことが大切です。
③法定相続情報一覧図を活用する
戸籍を何通も集める必要がなくなり、郵送申請が容易になります。
④Excelなどで管理表を作成する
どの銀行に申請したか、いつ届いたかを一覧化しておくと便利です。
9.まとめ:正確な残高証明書が相続税申告の第一歩
残高証明書は、相続税申告や遺産分割を正確に行うための基礎資料です。
特に、複数の口座や支店に資産がある場合、取得まで時間がかかることがあります。
相続発生後は通帳の確認だけで安心せず、早めに金融機関へ発行を依頼することが大切です。
税理士などの専門家を利用することで、残高証明書の取得だけでなく、財産目録の作成・評価・相続税申告まで一括サポートも可能になります。
当法人では、相続税申告の実績豊富な税理士が、必要書類の収集から申告書の提出まで丁寧にサポートいたします。
「何から始めたらいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
※2025年10月時点での情報です。
相続に関する無料相談実施中

相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>
お気軽にご相談ください
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台MTビルSOUTH4階
TEL:0120-311-315
FAX:022-295-1372
[受付時間]
平日9:00~18:00(受付:9:00~17:30迄)
土曜9:00~17:00(要予約)