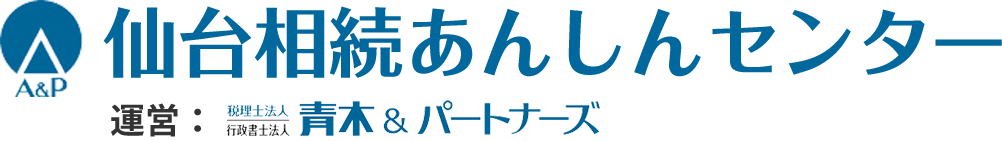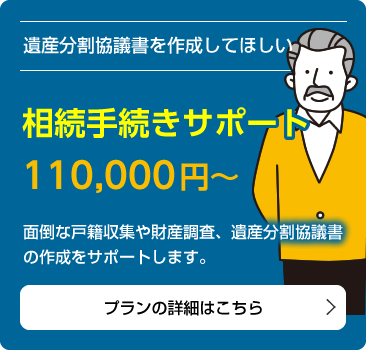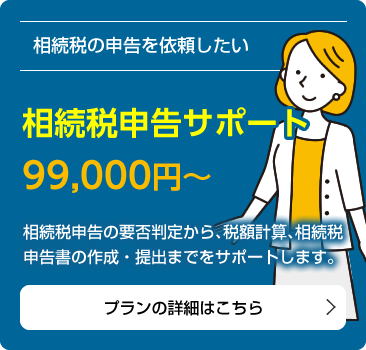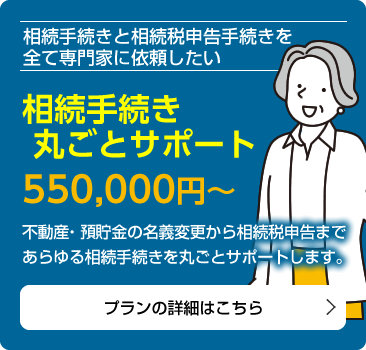自筆証書遺言の書き方とは?法的に有効にするための5つのポイント
ホーム > 相続豆知識 > [遺言] 自筆証書遺言の書き方とは?法的に有効にするための5つのポイント
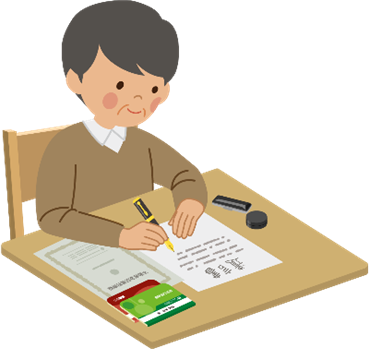
「遺言」と聞くと、「大金持ちや資産家が書くもの」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、家族がもめないように、自分の思いを形に残すという意味でも遺言書はとても重要な役割を果たします。
この記事では、遺言の中で最も手軽に作成できる「自筆証書遺言」について、法的に有効な書き方や注意点をわかりやすく解説します。
1.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、その名の通り、全文を自分の手で書く遺言書のことをいいます。
公正証書遺言のように公証人を通さず、紙とペンがあればいつでも自宅で作成できるのが大きな特徴です。費用もほとんどかからないため、最も多くの方が取り組みやすい方法といえるでしょう。
ただし、その分法律で決められたルールを守らないと無効になるリスクも高く、十分な注意が必要です。
2.自筆証書遺言を法的に有効にするための5つのポイント
法的に有効な自筆証書遺言を作成するために、必ず押さえておきたいポイントを5つご紹介します。
① 本文・日付・氏名をすべて「自筆」で書く
まず何よりも大切なのは、遺言の本文・日付・氏名を全て手書きすることです。パソコンで作成したものや他人に代筆してもらったものは無効になります。
※2020年の民法改正により、財産目録のみパソコンや通帳コピーの添付も可能になりましたが、これについては後ほど詳しく説明します。
② 日付は「特定できる形」で記載する
「令和7年7月16日」や「2025年7月16日」のように、年月日が特定できる形式で書く必要があります。
NGな例→「令和7年7月吉日」「令和7年夏の日」
こうした曖昧な日付は、遺言がいつ書かれたものか判断できず、無効とされる恐れがあります。
③ 氏名を署名し、印を押す(認印でもOK)
自筆で署名したうえで、押印(実印・認印どちらでも可)が必要です。法律上は認印でも問題ありませんが、トラブル防止のため実印を推奨します。
拇印・指印も有効とされる場合がありますが、真正性が疑われるためなるべく避けましょう。
④ 財産目録の作成方法に注意(自筆でなくてもOK)
2020年の法改正により、財産目録は自筆でなくてもよいとされました。つまり、Excelなどで作成した表や、不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなどを添付することが可能になりました。
その代わりに重要になるのが各ページへの署名・押印です。
各ページに押印がないと、そのページは無効扱いとなる可能性があります。
⑤ 作成後の「保管」と「検認手続き」に注意
自筆証書遺言を自宅で保管していた場合、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
この検認とは、遺言書が改ざんされていないかを確認する手続きです。検認が済まないと、相続手続きが進められません。
しかし、2020年7月から始まった法務局での自筆証書遺言保管制度を利用すれば、検認が不要となります。制度を利用すれば、紛失・改ざんの心配も軽減され、非常に便利です。
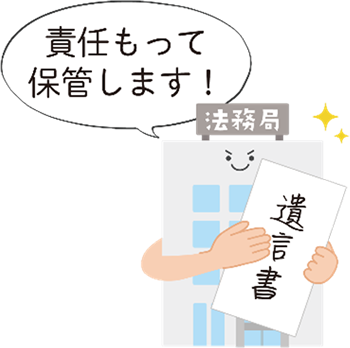
自筆証書遺言保管制度
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 紛失・改ざんの心配がない | 内容の法的チェックはされない |
| 家庭裁判所の「検認」が不要になる | 保管後に別の遺言を作成すると、どちらが有効か争いになる場合がある |
| 相続人が「遺言の有無」を確認できる | 保管後の閲覧は本人でも要申請 |
3.自筆証書遺言の有効性チェックリスト
以下のチェックリストに沿って、書いた遺言書が有効なものになっているか確認しましょう。
☑ 本文が自筆で書かれているか
全文・日付・氏名が手書きになっているか確認する。
☑ 日付の記載は正確か
「吉日」など曖昧な表現を避け、「〇年〇月〇日」と正確な日付を記載する。
☑ 押印があるか
シャチハタは避け、実印または認印を使用する。
☑ 財産目録の署名に押印があるか
パソコン作成の場合、各ページに署名・押印をする。
☑ 内容は具体的か
「自宅」や「預金」など曖昧な表現ではなく、詳細に特定できるよう記載する。
[例①]
×「長男に自宅を相続させる」
〇「〇市〇町〇番地の土地建物(登記簿記載)を長男〇〇に相続させる」
[例②]
×「次女に〇〇銀行の口座を全て渡す」
〇「下記に記載する〇〇銀行における預金口座のすべての預金債権を次女〇〇に相続させる」とし、預金口座一覧を添付する。
☑ 作成した遺言書の保管場所は明確か
家族が見つけやすい場所に保管し、所在を明確にしておく。
相続人の手間を減らすため、法務局での保管制度の利用も検討する。
4.自筆証書遺言はどんな人におすすめ?
費用をかけずに遺言を作成したい人
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば作成でき、公証人報酬や証人手配も不要です。経済的な負担を抑えて意思を残したい方に向いています。
財産内容や相続人が比較的シンプルな人
相続人が配偶者と子1人などで構成が単純、かつ遺産も預金や自宅程度で複雑でない場合、書式のミスが起こりにくく、自筆での作成が現実的です。
繰り返し見直し・更新をしたい人
状況の変化に応じて書き直したい場合、公正証書より自筆証書の方が柔軟です(ただし破棄や旧遺言の扱いには注意が必要です)。
急ぎで遺言を残す必要がある人
病気などで時間的猶予がない場合、自宅で即日作成できる点は大きな利点です。最低限の形式を守れば法的効力も生じます。
財産配分ではなく「感謝の気持ち」や想いを伝えたい人
自筆の温かみを大切にし、家族へのメッセージも含めて書きたい方には適しています。公正証書ではこうした“気持ち”の表現は形式的になりがちです。
法務局の保管制度を利用できる人(2020年以降)
令和2年からは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。これを利用すれば、紛失・改ざん・検認手続のリスクが大幅に減少します。
5.専門家のサポートも活用を
自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に始められる一方で、書き方にミスがあると無効になるリスクもあります。書き方のルールが分かっても、いざ書こうとすると不安になる方も多いはずです。
当法人では、相続に関する無料相談を承っております。
「何から始めたらいいのかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。
※2025年7月時点での情報です。
相続に関する無料相談実施中

相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>
お気軽にご相談ください
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台MTビルSOUTH4階
TEL:0120-311-315
FAX:022-295-1372
[受付時間]
平日9:00~18:00(受付:9:00~17:30迄)
土曜9:00~17:00(要予約)